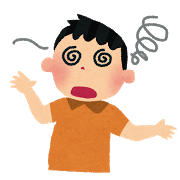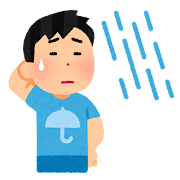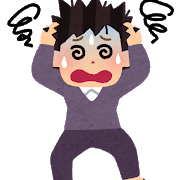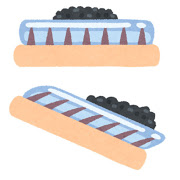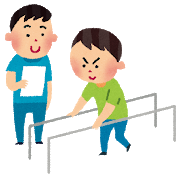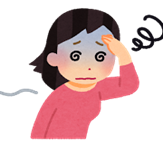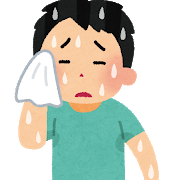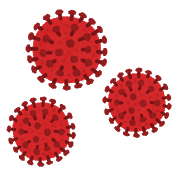疾患案内
めまい・ふらつきでお悩みの方へ
当院では、めまい相談医(日本めまい平衡医学会)(サイト)取得の上、専門性を向上させ適切な診断治療と医療連携をできるように努力研鑽しています。
『耳』『脳』『全身』またはその他なのか判断し、脳からの可能性の時は早期に、総合病院または脳外科へ紹介させていただきます。
当院のめまい対応の方針については次のサイトで確認して下さい。
☞ めまい・ふらつき(吉 耳鼻咽喉科アレルギー科HP)
◆ めまいの原因は複雑混在:どう対応? 20230606 New
◆片頭痛は国民の10人に1人程度で非常に多い疾患です。片頭痛にめまい症状が多いことはあまり知られていません。片頭痛関連のめまい疾患の前庭性片頭痛の診断基準が確立されたのは2012年ごろで最近のことです。頭痛よりめまい症状が前面にでてくるので耳鼻咽喉科に受診されることが多い疾患ですが、認識不足や診断が複雑のため原因不明のめまいやメニエール病として診断されていることもあります。耳鼻咽喉科医からみた片頭痛とめまいについての解説です。
☞ 耳鼻咽喉科医からみた片頭痛:関連めまい(院長コラム)20220316
◆メニエール病は、よく知られた病名ですが、実際は稀な疾患です。しかし発症すると、反復する突然のめまい・吐き気などに長期に悩まされます。働き盛りのストレスを抱えた中年ごろに発症が多くなります。進行すれば難聴が進行して回復しません。耳鳴りにも悩まされます。性格がまじめで、不眠・ストレス・自律神経症状を背景に抱えている方に多い傾向があります。通常は、薬と生活睡眠指導などでコントロールできることがほとんどですが、一部の方はコントロールが難しい場合もあります。最近、中耳加圧療法が注目されています。
☞ メニエール病の新しい治療法:中耳加圧療法(院長コラム)20210920
◆良性発作性頭位性めまい症(BPPV)は、めまい疾患の約半分程度を占めるありふれた疾患です。通常の症状である回転性めまいでないことも多く、また検査のタイミングでは、検査をしてもわからないことも多く経験します。反復するけれど自然治癒することも多いため、疲れ、更年期、年のせい、睡眠不足などと自己判断してしまうこともあります。難聴・耳鳴り症状はなく画像検査や聴力検査・採血検査などしてもわかりません。原因不明のめまい・ふらつきとして診断されていることもあります。
次のコラムで奥が深いBPPVについて解説しています。
☞ あなたのめまいは更年期or年のせい?BPPV(当院コラム)20210513
◆耳からのめまいを疑う時、難聴・耳鳴り・耳閉感は重要な症状です。若い人に比較的多い、急性低音障害型感音難聴という病態があります。ストレス・気象など関連して、耳閉感を訴える病気ですが、メニエール病や突発性難聴の初期のこともあり注意が必要です。
☞ 若い人にも稀ではない耳閉感・難聴(当院コラム)20200813
◆高齢者は、ふらつき・転倒のリスクが高く、寝たきりや致死的な状態の誘因となります。若い人には少ない基礎疾患、多くの薬、加齢変化が影響し診断を難しくします。注意する疾患、日常の注意点、対策などまとめてみました。
☞ 診断が難しい高齢者めまい(当院コラム)20200708
◆めまいの有訴率は高く、成人では10~30%、70歳以上では30~50%、慢性めまいでは20~25%程度『めまい症』と診断され原因不明の状態が多く存在します。最近、PPPDと言い慢性機能性めまいの疾患概念が国際的に確立され、今まで原因不明のめまい症と考えられていたものの中にかなり含まれていることがわかってきました。PPPDについての解説です。
☞ 診断がつきにくいめまい症:PPPD(当院コラム)20200528
◆お子さんのめまい・ふらつき・立ちくらみは以前から起立性調節障害と考えられてきましたが、片頭痛が関連するめまいや腹部症状が多く関わっていると分かってきました。次のコラムで解説しています。
☞ お子さんのめまい・ふらつき・立ちくらみ(当院コラム)20200330
◆耳鼻咽喉科医が診察することが多い回転性のめまいの最近の三つの話題と生命に関わるめまいを見分けるうえでの注意点の話です。
②メニエール病の中耳加圧療法
③片頭痛とめまいの関係
④危険なめまいの見分け方(注意点)
☞ 回転性めまいの話題と注意点(当院コラム)20191016
◆めまい・ふらつきは女性に多く反復することが多い症状です。月経異常、更年期障害、片頭痛、肩こり関連との関係も深く、自律神経症状の一つして認めることもあります。漢方薬が効果を発揮することが多い領域です。女性のめまい・ふらつきと漢方についてまとめてみました。難治化しやすいメニエール病、肩こり関連めまいは詳細に解説しています。
☞ 女性のめまい・ふらつき:漢方編(当院コラム) 20190817
◆ めまい・ふらつきの訴えは、男性より女性が約2.5倍多く認められます。
次のサイトで、女性のめまい・ふらつきと高齢期での転倒についての概要(思春期の起立性調節障害、良性発作性頭位性めまい症、更年期障害、老人性平衡障害、フレイル・ロコモ)とその対策をまとめてみました。
☞ 女性のめまい・ふらつき・転倒(当院コラム)20190619
◆ めまいだけでなく、頭痛も女性は男性より約2.5倍多く認められます。女性に多く、頭痛・めまい・ふらつきが共存しやすい疾患(前庭性片頭痛、月経関連片頭痛、月経前症候群、更年期障害、緊張性頭痛:肩こり関連めまい、起立性調節障害、心因性めまい:PPPD)をまとめてみました。
☞ 女性とめまい・ふらつき・頭痛(当院コラム)20190804
正しい知識を学び、服用の不安を少しでも減らせるように次のサイトにまとめてみました。
☞ 妊婦&授乳と薬:飲んで大丈夫?(当院コラム)20190226
◆頻度は低いのですが、命に関連するめまいは、耳からではなく、脳や不整脈・心疾患に関連するめまいです。 もう一つ命に関連するめまい・ふらつきは、5月の運動会頃から9月頃まで注意が必要な熱中症です。熱中症の初期症状は、ふらつき・めまい・立ちくらみや足のつり・気分不良です。高齢者は夜間に多く発症しています。
もう一つ命に関連するめまい・ふらつきは、5月の運動会頃から9月頃まで注意が必要な熱中症です。熱中症の初期症状は、ふらつき・めまい・立ちくらみや足のつり・気分不良です。高齢者は夜間に多く発症しています。
次のサイトで、熱中症への対応と予防のための効率良い暑熱馴化について説明しています。
☞ 鼻と眩暈と熱中症:暑さ対策は大丈夫?(当院コラム)20190429
◆思春期になると、急に大人への成長が進み、心と体のバランスが崩れ、自律神経障害による立ちくらみ・ふらつき、起立性調節障害、頭痛、腹痛および生理不順など生じてきます。これらの症状がきっかけで朝起きれなくなり、不登校、夜更かし、スマホ・ゲーム依存へ進展し、さらに朝起きれず悪循環となることもよくあります。思春期のふらつき・立ちくらみの対応を漢方療法や生活・食習慣の改善について解説しています。
☞ よくわかる子供の漢方:起立性調節障害;ふらつき・頭痛・腹痛(当院コラム)20180708
◆古来から、めまい、頭痛、耳閉感、神経痛、喘息など低気圧・台風との関連を経験してきました。これらは気象病と言われています。
次のサイトでは、我々の経験、東洋医学、西洋医学の関連性と対策を説明しています。
☞ 台風と気象病(めまい・耳閉感・頭痛)(当院コラム)20171023
アレルギーの各疾患でお悩みの方へ
◆当院のアレルギー疾患への対応(診察の流れ、できる事できない事)について説明しています。
☞ 当院のアレルギー対応(当院HP)
◆吸入薬は、内服と違い使い方が理解できなければ効果ありません。喘息・咳喘息の吸入療法で、以前からの方法にちょっとしたコツを習得すれば50%ほど効果がアップすることがわかってきました。
ホー吸入で薬効果をより良く実感:喘息・咳喘息の方へ 20230528 New
◆花粉症関連の最近の当院コラム
☞ マスクで発症予防:小学生スギ花粉症(20230120)
☞ 花粉飛散情報の変化&知っておくこと!!(20220306)
☞ 早くから始めるスギ花粉症治療:初期療法(鹿児島)(20220206)
☞ 急増するスギ花粉症にどうする?(舌下免疫療法:Afterコロナ)(20210903)
◆喘息は様々な病態があり、それぞれの特徴に合わせた対応が必要になります。乳幼児の喘息の診断は難しく、症状としての喘鳴(ぜんめい:ゼーゼー)として最初は経過を見ることから始まります。乳幼児・学童・成人(男女)・老人の喘息のタイプ分類についての解説です。
☞ あなたの喘息は何タイプ?成人編(当院コラム)20201120
☞ お子さんの喘鳴(ぜんめい)は何タイプ?(当院コラム)20201108
◆アレルギーマーチ(アトピー性皮膚炎➡食物アレルギー➡喘息・アレルギー性鼻炎結膜炎)の発症・進展の予防、スキンケア・離乳食を遅らせず食べること・舌下免疫療法・ダニ対策などについて、アレルギー全般を考えた生後から思春期にかけての予防と対応を解説。
☞ アレルギーマーチの予防と対策(当院コラム)20190908
◆子供の食物アレルギー予防の三つのポイントについて簡潔に説明
☞ 子供の食物アレルギー(当院HP)
~~鹿児島県で食物経口負荷試験医療機関のお探し方は次を参考にしてください~~
*鹿児島県の食物経口負荷試験実施医療機関(サイト)
◆スギ花粉症・ダニのアレルギー性鼻炎の体質改善を目的とした新しい治療法です。
☞ 舌下免疫療法(スギ・ダニ)(当院おしらせ・疾患予防)20190414
◆ダニ関連の喘息・アレルギー性鼻炎・結膜炎の治療で重要なのは、薬より原因となるダニの駆除・増殖予防とアレルゲンとなる死骸・フンの対策です。薬に比べ即効性は無く軽視しがちです。実践ダニ対策では、動画を使い、わかりやすく動機づけを考えて解説しています。
☞ 実践ダニ対策(当院コラム)20190920 new
◆スギ花粉対策の第一はスギ回避対策と自己管理です。ネットのHPを利用すれば、効率が上がります。スギ林が多いければスギ花粉症患者が多いわけではありません。環境因子が大事です。次のサイトで説明しています。
☞ 自分で行うスギ花粉・鼻炎結膜炎の対策(黄砂・PM2.5含む)(当院コラム)20190127
◆運動は心身の発達や心身の健康維持のため大切です。運動で咳が出たり、胸の圧迫感・ゼーゼーがでて喘息症状を誘発することがあります。次のサイトで、運動誘発性の喘息症状、鼻炎、喉頭の病気について説明、トップアスリートにはドーピングに配慮した服用が必要になり対応を説明しています。
☞ 運動・アスリートと喘息・鼻炎(当院コラム)20190916 new
◆鼻アレルギー、好酸球性副鼻腔炎の悪化は喘息を悪化させます。鼻風邪のライノウイルス感染は、喘息の増悪因子となります。鼻・副鼻腔炎は、後鼻漏・口呼吸から、咳や喘息に関与します。鼻のコントロールは喘息症状を改善させるのに重要な要素です。秋の喘息は、ダニの影響とライノウイルス感染に注意します。
☞ 鼻と秋の喘息(当院コラム)20171025
◆生活習慣病対策は、国を挙げて行われていますが、喘息にも関係することがわかってきました。次のサイトで肥満と喘息の関係と対策を詳細に説明。
☞ 肥満と喘息:ダイエットで喘息が治る?20190507
◆最近増加している新型の副鼻腔炎が好酸球性副鼻腔炎です。好酸球が増加するダニ・スギなどのアトピー型とは違う機序で起こり、ダニと同様に好酸球が増殖する病態です。喘息・嗅覚障害と合併することが多く、中年以降の成人女性に増えている副鼻腔炎です。次のサイトで、色々な副鼻腔炎の中で、好酸球性副鼻腔炎について説明しています。
☞ あなたの副鼻腔炎は何タイプ?(当院コラム)20190602
◆寒暖差で、鼻アレルギーと同じ症状がでる人を『寒暖差アレルギー』と呼ぶようです。実態は、ダニなどのアレルゲンと直接には関係ない『血管運動性鼻炎』を指すようです。次のサイトで実態を医学的に解説しています。
☞ 寒暖差アレルギー(当院コラム)20171024
◆成人の2か月以上持続する咳の原因の半分は咳喘息で、アトピー咳嗽・喉頭アレルギーを入れると、慢性咳嗽の7割程度は、アレルギー・好酸球性気道炎症が原因となります。これらに喘息が加えるともっと増えます。次のサイトで当院の咳の方針と各世代での対応を説明しています。
☞ 咳(当院HP)
◆最近は、アレルギー、生活習慣、加齢による咳が増加しています。実際の咳への対応について時系列で解説しています。
☞ 増え続ける咳の患者さんたち(当院コラム)20180112
◆口腔アレルギー:
食べたものが原因で食物アレルギーが起こると考えるのが一般的と思われます。最近では、成人の食物アレルギーでは、食べなくても起こる食物アレルギーが多くなっています。花粉・食物アレルギー症候群【Pollen-food-allergy syndrome:PFAS】と言います。口腔内に限局したアレルギーを生じるので口腔アレルギー症候群とも呼ばれます。
次のコラムで秋の花粉との関連で説明しています。
☞ 秋の花粉とキウイ&スパイスアレルギー(当院コラム)20171105
◆アトピー性皮膚炎の西洋的治療は九州大学皮膚科のHP(サイト)がよくできていますので、確認しましょう。
『アトピー性皮膚炎には、適切なステロイド塗布とスキンケアが主の治療となります。補助的な役割となりますが、以下のサイトでは、漢方によるアトピー性皮膚疾患への対応について解説しています』
◆皮膚は内臓の鏡!次のサイトは、漢方で心と腸内細菌を整え、子供の皮膚疾患を少しでも良い方に向かわせる話です。
☞ よくわかる子供の漢方:アトピー・蕁麻疹・よだれ皮膚炎・水いぼ(当院コラム)20180608
◆人類発展・赤ちゃん・脳にとって汗をかくことの重要性やアトピーと汗の新しい考え方、漢方での多汗症、西洋医学の補助として乾燥肌への対応の仕方について説明。
☞ 汗とアトピー、そして漢方(当院コラム)20180815
新型コロナ関連
作成中
◆ 新型コロナ後遺症:どうしたらよいの?2022年9月2日
◆ 意識しないとわからない嗅覚障害:sniff & smell 2022年9月18年
◆ 抗原定性検査の利用拡大:コロナ診療の現場から 2022年8月21日
◆ バイデンも行うコロナワクチン4回目接種:限定的効果 2022年5月29日
◆ コロナ重症化リスク抑制指標:抗体測定(定量) 2022年1月23日
◆ 新型コロナワクチン後の頭痛・倦怠感の8割弱は心の問題!! 2022年1月30日
◆コロナワクチン関連の心筋炎:運動していいの?2021年9月6日
◆若年者の血管迷走神経反射(脳貧血)を防ぐには!!(コロナワクチン)2021年9月3日
◆コロナワクチンのアナフィラキシーが、女性になぜ多い?(対応)2021年7月25日
◆お子さんの新型コロナ対策は大人から!!2021年3月14日
◆新型コロナ対策:性差・子供の視点から2021年2月10日
◆インフル・新型コロナに解熱鎮痛剤は大丈夫?2020年3月20日
鼻疾患・嗅覚障害
◆子供さんの病気は、結膜炎・中耳炎・咽頭扁桃炎・咳・痰・喘息・いびき・口呼吸・無呼吸など、大人より鼻と関連する病気がよくおこります。
乳幼児の病気は鼻から!! 20230528 New
◆嗅覚障害は、意識しないと自分でわかることが難しい疾患です。嗅覚障害のことを自分でわかっていない高齢者や子供さんは多く、鼻の訴えでクリニックで診察を受け初めて気づくことはよく経験します。匂いを意識すること、日常生活で嗅ぐ習慣を身に着けることが大事であるお話です。
➡意識しないとわからない嗅覚障害:sniff & smell(当院コラム) 20220918
◆かぜで鼻症状が悪化すれば副鼻腔炎が疑われます。
一昔前は蓄膿と呼ばれていましたが、今日、副鼻腔炎には小児・成人、急性・慢性の他に新型の好酸球性など様々な病態が存在し、病態により対応が異なってきます。
あなたの副鼻腔炎は何タイプか考えてみましょう。
➡あなたの副鼻腔炎は何タイプ?(当院コラム)
◆嗅覚障害は、
①中枢性(認知症、外傷、脳梗塞)
②嗅神経性(外傷、ウイルス感染)
③気導性(副鼻腔炎など)
に病態分類されます。
気導性は、副鼻腔炎・鼻炎の治療が優先されます。
嗅神経性は、神経再生を促す必要があり月~年単位で改善を期待する必要がありますが、今までエビデンスが高い治療はありませんでした。
最近、海外での匂いのトレーニング(嗅覚刺激療法)が注目され、日本でも行われるようになってきました。
次のサイトで、神経再生を促す自宅でも可能な匂いのトレーニングについて紹介しています。
➡においと学習効果(当院コラム)
◆スギが多い所に必ずしもスギ花粉症の方が多いわけでなく環境要因が重要な要因となります。
スギ花粉症のセルフケアから、黄砂、PM2.5との関係について次のサイトで説明しています。
➡自分で行うスギ花粉対策(セルフケア・黄砂・PM2.5)(当院コラム)
◆『寒暖差アレルギーがある』と患者さんからよく聞きます。
医学的には寒暖差にアレルギー反応はなく、血管運動性鼻炎を指すようです。
次のサイトで医学的な解釈を説明しています。
◆鼻アレルギーや好酸球性副鼻腔炎の悪化は喘息の悪化をもたらします。
次のサイト解説しています。➡ 鼻と秋の喘息(当院コラム)
声がれでお悩みの方へ
◆声がれの当院の基本方針は
声がれ(当院HP)
◆高齢者の声がれは嚥下障害とリンクすることが多くあります。声がれは悪い物ではと不安にもなるものです。高齢者の声がれで最も多く、誤飲性肺炎の初期症状として重要な声帯萎縮について対策など解説しています。
👉 高齢者の声がれは、肺炎の前兆? 声帯萎縮(院長コラム)20210515 NEW
◆声をよく使う方の声の衛生状態を良くするには、のどの加湿とのどに負担をかけない発声が重要。次のサイトで詳細を説明。
👉 自分で行う声がれ対策(声の衛生)(当院コラム)20190102
◆職業や趣味で声を使う方の声がれは、声の衛生だけではうまくいかないことも多くあります。望ましくない発声行動を時間をかけて変えていく必要が出てきます。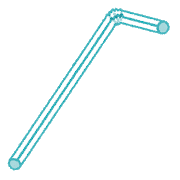 基本は腹式呼吸・喉頭負荷軽減・鼻腔咽頭共鳴を促進させ声帯振動の正常化をはかります。ハミング(共鳴法)とストロー発声はお勧めです。
基本は腹式呼吸・喉頭負荷軽減・鼻腔咽頭共鳴を促進させ声帯振動の正常化をはかります。ハミング(共鳴法)とストロー発声はお勧めです。
👉 自分で行う医学的ボイトレ(音声治療:当院コラム)20190119
◆高齢者の咳と声がれの注意点としてドライマウスと嚥下機能障害が背後に隠れている可能性があります。次のサイトで対策を説明しています。
👉 自宅でできるドライマウス対策(当院コラム)
👉 自宅できる誤嚥性肺炎予防(当院コラム)20180831
« Older Entries