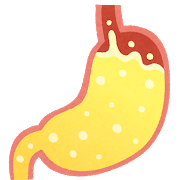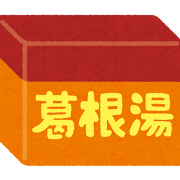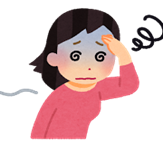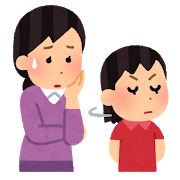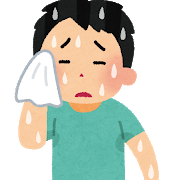疾患案内
ドライマウス・窒息・誤嚥性肺炎
のどは、声を出し、息をして、食べる行為を意識せず行っています。
のどの奥は、声を出す喉頭の後ろに食道の入り口があるため食べ物が気管に入らないように、食事の時は声帯と喉頭蓋が閉じ、間違って入ろうとすれば、咳で防いでいます。
これは非常に複雑な行為で、加齢や病気で少しずれが生じるだけで窒息・誤嚥性肺炎の恐れが出てきます。
◆高齢者の声がれは嚥下障害とリンクすることが多くあります。声がれは悪い物ではと不安にもなるものです。高齢者の声がれで最も多く、誤飲性肺炎の初期症状として重要な声帯萎縮について対策など解説しています。
👉 高齢者の声がれは、肺炎の前兆? 声帯萎縮(院長コラム)20210515 NEW
◆ 加齢・ストレス・薬物などの影響で口腔乾燥を訴える方が増えています。
ドライマウスがあれば、飲み込みずらさ、声がれ、味覚低下、のど舌の違和感や痛みが出現し、細菌がのどに付着しやすくなります。
次のサイトで、自宅で可能なドライマウス対策について説明しています。
☞ 自宅でできるドライマウス対策(当院コラム)
声がれがあれば、使い過ぎ、風邪、喉の癌や病気、嚥下機能の低下、ドライマウス、稀に脳や胸の病気の可能性もあります。
日頃からのどのケアを心がけましょう!次のサイトで説明しています。
☞ 自分で行う声がれ対策(声の衛生)(当院コラム)
◆ のどのケアで重要なのは加湿です。
特に、暖房を使い空気が乾燥する秋から冬にかけて加湿器は重要な役割をはたします。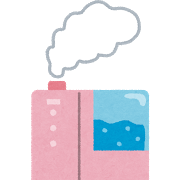
間違った加湿器の選択をすると過敏性肺炎やレジオネラ肺炎を起こし死亡することもあります。
病気ならない加湿器の選択について次のサイトで説明しています。
☞ 病気にならない加湿器の選択(当院コラム)
高齢化ともに窒息死が、交通事故の2倍まで増加、そのほとんどが嚥下機能が低下した高齢者です。
救命のカギは、自宅や現場での速やかな異物除去です。
自宅でできる窒息対策を次のサイトで説明しています。
☞ 自宅でできる窒息対策:交通事故より多い窒息死(当院コラム)
◆ 日本人の全死亡原因の3位は肺炎で、
その多くが誤嚥性の関与が考えられています。
次のサイトで動画を利用して説明しています。
☞ 自宅でできる誤嚥性肺炎予防(当院コラム)
◆ 声を上手に出すことは、嚥下機能のリハビリに有効です。
次のサイトで、声を上手に出すヒントを多くの動画を使い説明しています。
腹式呼吸の要領の詳細や声帯萎縮に対しての嚥下リハの方法も説明しています。
☞ 自分で行う医学的ボイトレ(音声治療)(当院コラム)
咳でお悩みの方へ
咳
◆咳は、風邪をひいて最も長く続き患者さんが最も煩わしく感じる症状の一つです。戦前戦後は結核や感染症が主な原因でしたが、現在は、アレルギー、生活習慣病、加齢による咳が増加しています。次のサイトに、当院の咳に対する方針と咳の総論・各世代での対応を記載しています
◆風邪の咳は、1週間以内をピークに数週間で改善すること、湿性か乾性かの咳の区別の重要性、風邪薬や咳止めの使い過ぎの問題点、発症2か月を目安に咳の治療方針は変わることなどを、次のサイトで詳細に説明しています。
➡ 増え続ける咳の患者さんたち(当院コラム)
◆咳喘息や喘息の治療にアレルギー性鼻炎や鼻疾患を同時に治療することの重要性(one airway, one disease )を次のサイトで解説しています。
➡ 鼻と秋の喘息(当院コラム)
◆胃酸の逆流は様々な症状を引き起こします。最近、体重が気になる方や背中が曲がってきた年配の方、長引く咳のお子さんから大人まで次のコラムで確認しましょう。
➡胃酸の逆流と耳・鼻・のど・呼吸器(当院コラム)2019年11月23日
◆生活習慣病対策は、国を挙げて行われていますが、喘息にも関係することがわかってきました。次のサイトで肥満と喘息の関係と対策を詳細に説明。
➡ 肥満と喘息:ダイエットで喘息が治る?(当院コラム)
◆漢方で、咳をどう対応するか?
*成人の感冒と咳については次のサイトで説明しています。
➡よくわかる風邪の漢方(当院コラム)
*小児の咳&喘息と中耳炎、副鼻腔炎、鼻炎、扁桃炎などは次のサイトで説明。
➡ よくわかる子供の漢方:中耳炎・鼻・のど・肺(当院コラム)
漢方診療を希望される方へ
当院では、漢方外来は設けていませんが、症状に合わせ、西洋・東洋のどちらが良いか、または同時に対応すべきか考慮して診察しています。
診察の時に、申し出ていただければ、漢方医学主体での診察をしています。急性疾患、癌の疑いなどで、明らかに西洋医学が望ましいときは助言しています。
➡当院の漢方診察と漢方処方についての考え方は、次のサイトを見てください。
◆ストレスを感じると、胃の調子が悪くなったり、こころと口・のど・お腹は、古来からから相関がありました。最近は、脳腸相関として注目されています。漢方・東洋医学では、半夏厚朴湯を代表に2000年ほど前から、『心身一如』として、心とのどの異常感、胃腸障害、不眠を同時に治療していく治療体系が存在していました。ストレスと機能性胃腸障害・ヒステリー球に舌痛症を加えて心身一如としての漢方を取り入れて解説してみました。
☞ ストレスとお口・のど・おなか&漢方 20191221 New
◆めまい・ふらつきは女性に多く反復することが多い症状です。月経異常、更年期障害、片頭痛、肩こり関連との関係も深く、自律神経症状の一つして認めることもあります。漢方薬が効果を発揮することが多い領域です。女性のめまい・ふらつきと漢方についてまとめてみました。
☞ 女性のめまい・ふらつき:漢方編 20190817 new
➡次のサイトでは、風邪の漢方を、中医学、傷寒、温病の考えで説明しています。テレビの番組を紹介しながら、かぜの時の漢方の発汗療法と自宅でどうすればよいか解説!
☞ よくわかる風邪の漢方(当院コラム) 20171130
➡漢方処方の前に、食養生、生活習慣の是正、親子の交流が重要であること!子供への漢方の飲ませ方の工夫と子供の漢方の総論を次のサイトで解説しています。
よくわかる子供の漢方:服用法・子供の漢方総論(当院コラム)20180422
➡耳鼻咽喉科・呼吸器疾患は抗生剤使用が多く、薬剤耐性菌と抗生剤使用の問題点を解説。次のサイトでは、子供の漢方使用のメリットと使用法について詳しく解説しています。
よくわかる子供の漢方:中耳炎・鼻・のど・肺(当院コラム)20180516
➡次のサイトでは、食が細いよく風邪をひくお子さんの食養生と漢方での対応について解説!胃腸炎、便秘での漢方での対応も述べています。
よくわかる子供の漢方:食が細い、胃腸炎、便秘(当院コラム)20180701
➡次のサイトでは、半成人以降のふらつき、生理不順、頭痛、心身症、自律神経症状への幼少時の感染症からの病気の変化を解説!漢方での対応を述べています。親子関係が難しくなるときでもあります。
よくわかる子供の漢方:起立性調節障害;ふらつき、頭痛、腹痛(当院コラム)
20180708
➡次のサイトは、疳が強いお子さんの漢方の解説です。
よくわかる子供の漢方:感覚過敏、夜泣き、夜驚症(当院コラム)
20180505
➡皮膚は内臓の鏡!次のサイトは、漢方で心と腸内細菌を整え、子供の皮膚疾患を少しでも良い方に向かわせる話です。
よくわかる子供の漢方:アトピー・蕁麻疹・よだれ皮膚炎・水いぼ(当院コラム)20180608
➡人類発展・赤ちゃん・脳にとって汗の重要性やアトピーと汗の新しい考え方、漢方での多汗症、西洋医学の補助として乾燥肌への対応の仕方について説明。
汗とアトピー、そして漢方(当院コラム)20180815
Newer Entries »