めまい・ふらつき
めまい相談医について
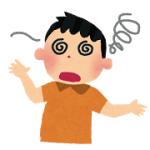 日本めまい平衡医学会では平成23年にめまい相談医制度を発足しています。
日本めまい平衡医学会では平成23年にめまい相談医制度を発足しています。
めまい臨床の専門的知識と高度の診療技術をもつ会員を対象に講習会と試験を受け合格者を認定する制度です。
めまい・ふらつきを訴える方に、医療機関・医師の選択に関する情報提供をすることを目的としています。
始めに:
交通網の発達、ストレス、高齢化社会が進むにつれ、めまいに悩む方たちも右肩上がりの増加を認めます。
めまいの診療は多科にわたり、耳、脳、循環器、貧血、筋力低下、心因性と広い視点で見ることが重要です。
当院では
めまい相談医を取得し、専門性を向上させ適切な診断治療および医療連携を皆様に提供できるように努力研鑽しています。
『めまい診療の流れ』
①めまい診療で最も重要なことは、患者さんから詳しく話を聞くこと(問診)です。一般問診とは別にめまい専門問診を作成し記載していただきます。
②「耳から」「脳から」「全身疾患」からの眩暈なのか、詳しく診察を進めていきます。
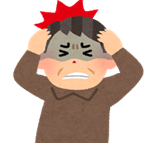 一般耳鼻科診察、手・足・眼球運動、舌の動き口腔内観察、軟口蓋や声帯の動き、嚥下機能、小脳機能など神経学的診察を進めます。
一般耳鼻科診察、手・足・眼球運動、舌の動き口腔内観察、軟口蓋や声帯の動き、嚥下機能、小脳機能など神経学的診察を進めます。注視眼振検査、head impulse test, skew deviation,起立・座位検査など組み合わせます。
この時点で脳からの可能性が高い方は 近医脳外科また総合病院に紹介させて頂くことがあります。
③立位が可能な方は、足踏み検査など平衡機能検査を行います。
④メニエ-ル氏病など内耳性めまいを診断するため、聴力検査を行います。
⑤最後に、めまいの詳細な診断を目的として、めまいの異常所見を見つけやすくする 赤外線カメラ下の眼振検査をおこないます。
このとき良性発作性頭位性めまい症の診断がつけば、診断に引き続き治療として浮遊耳石置換法(Epley法など)を 行うことがあります。
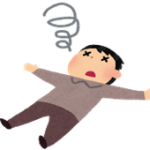 ※上記4、5の検査診察は時間を必要とし、また体調不良ではできないことがあり、後日に検査を組むことがあります。
※上記4、5の検査診察は時間を必要とし、また体調不良ではできないことがあり、後日に検査を組むことがあります。※上記5(めまい眼振検査と耳石置換療法)の検査・治療は、時間と人手を要すため混雑する平日午後4時以降、土曜は原則行っていません。
⑥薬物療法・眩暈リハビリ:
適切な薬物療法を行ってもめまいはすぐに改善することは少なく、遷延するめまいやふらつきは、東洋医学的視点から漢方薬の併用や、前庭・眼および前庭・脊髄反射を利用してリハビリ指導を行い小脳での前庭機能の代償を促していきます。
実際の診療では、原因不明のめまいの患者さんは多く、原因不明の眩暈に対しても脳疾患など無ければ、経過観察や薬物療法で対応し長期的に判明することもあります。
⑦その他に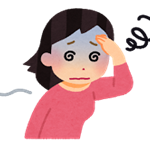
貧血や全身状態を把握するための採血
立ちくらみの検査
心因性めまいの診断のため 心理テスト
薬手帳を確認し薬剤性めまいのチェック
を適宜取り入れ対応いたします。
『中枢性(脳梗塞や出血)めまいについて』
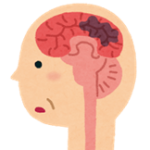
めまい以外に、運動・感覚障害や呂律異常、頭痛、顔面麻痺、二つに見えるなどあれば、中枢性をすぐ疑いますが、めまい・ふらつきのみの症状では脳以外の可能性が高く、中枢性は多くはありません。
しかし、ある報告では、小脳梗塞でめまいのみは11%、その96%が後下小脳動脈領域の梗塞です。
小脳出血でも頭痛伴わない回転性めまいが稀にあります。
発症24時間以内(特に早期6時間以内は)急性期脳梗塞の5.8~17%に、症状は明らかにもかかわらず、画像所見は異常を認めない偽陰性例があります。
経過観察の上、早めのMRI再検が必要となります。椎骨脳底動脈系は梗塞巣のサイズが小さく、MRIでの所見出現が遅くなります。
*高齢・糖尿病・高血圧・脂質異常症・肥満など動脈硬化の合併を疑わせる既往や発作性心房細動があるときは特に中性めまいの注意が必要です。
『心因性めまい』
 眼振検査や神経学的所見、頭部画像検査で異常を認めませんが、ふらつきやめまいの訴えが長期に持続することがあります。
眼振検査や神経学的所見、頭部画像検査で異常を認めませんが、ふらつきやめまいの訴えが長期に持続することがあります。
回転性より浮動性めまいが多く、不眠などによる自律神経異常の関与が強くなります。
心因性めまいを疑い、精神症状を確認し心理テストを施行しますが、有用な検査がありません。
身体動揺が開眼・閉眼ともに大きく、大きな揺れを示しても転倒がおこらないなど参考にしていきます。
不安障害の70%、身体表現性障害(症状はあるが、それに見合う体の異常がない疾患)の80%、うつ病の7~30%はめまいの訴えの報告があります。
最初は、通常のめまい疾患が、長期になると予期不安から心因性めまいに移行することもあります。
重症の方は、心療内科・臨床心理士など紹介することがあります。
日常生活が出来なくなるめまい・ふらつきを皆さまと考えていきたいと思います。

