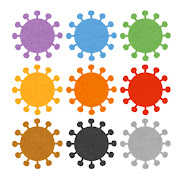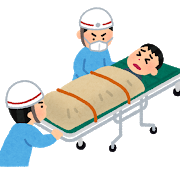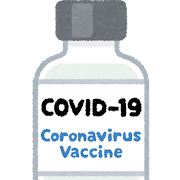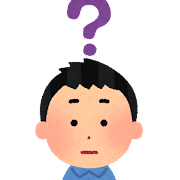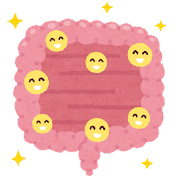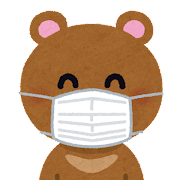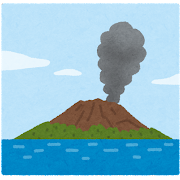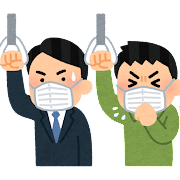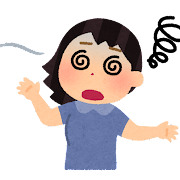院長の健康情報コラム
インフルとコロナどちらが怖い
◆コロナ5類以降後、様々な感染症で混沌
2023年5月コロナ5類以降後、感染症の流行が、2019年までの常識が通じなくなっています。集団免疫(人口の一定割合以上人が免疫を持つことで流行抑止)の低下もあり、インフルは夏からずっと増加、タイプもA型が2種流行、B型が2024年早々から増加。他の通常疾患の感染症(溶連菌、プール熱など)も増加、致死率が高い人食いバクテリアと呼ばれる劇症型溶連菌感染も増加しています。溶連菌とプール熱のキットが不足して注文しても入ってこない状態です。咳止めが薬局で不足して入ってこないようです。
発熱などでクリニック受診すれば、インフル・コロナ同時迅速検査が行われます。2024年早々からコロナはオミクロンの変異株の免疫逃避が高いJN.1など増加しています。しかしコロナに関しては、オミクロン前の致死率が高い状態にはなっていないようです。
👉 2024年現在、インフル コロナどちらが、怖い病気でしょうか?
◆2022年前半のオミクロン初期では
➡インフルエンザと新型コロナの死亡者数の差は69歳以下では大きくない
➡新型コロナの軽症化
オミクロン株では以前のコロナと違い、肺炎、血症症、嗅覚味覚障害は低下して、咽頭痛、嚥下障害、ひどい喉頭炎が多く喉頭蓋炎(緊急入院する疾患)を呈することもあります。食事摂取できず体力が低下して持病の悪化による誤飲性肺炎、心不全などの合併症での悪化が目立つようになっています。コロナの死亡者は80歳以上の割合が目立っています。
新型コロナの罹患率は高いが、症状について一部の方を除き軽症化していて、当院は耳鼻咽喉科のこともあり、発熱が無く咽頭痛程度の方が多く自分がコロナとは思って受診されない方が多くいます。
2020年初期の新型コロナの致死率が高く(80代 15%、70代 8%)、恐れられた疾患でしたが、時を経て2022年以降オミクロン株に代わり、感染力は高くなっているが、死亡率は低下して インフルとほぼ同等に近い死亡リスクに変わってきました。
『初期のオミクロンとコロナ流行前のインフルの死亡率の比較報告』
2022年8月奈良県立医大の報告で
初期オミクロン株が主流となった2022年1月5日~7月5日の調査では以下のことが判明
*インフルエンザと新型コロナの死亡者数の差は69歳以下では大きくない
*乳幼児学童の死亡率はコロナよりインフルの方が少し高い
*70歳以上高齢になると死亡率はコロナの方がインフルより約2倍高くなっています。
*70歳以上では、インフル・コロナともに死亡率は急増してともに20代と比較しておよそ100倍以上の増加。
*インフル・コロナとも80歳以上になると70歳代の約5倍程度の死亡率に跳ね上がります。
*ワクチン接種率が向上して死亡率の低下あり
*オミクロン以降も小児は軽症が多い、オミクロン以降2022年から稀だがコロナによる小児の死亡例もあり
◆2023年5月コロナ5類以降 コロナとインフルの比較では
➡高熱を伴うことが多いインフルの方が辛く感じる方が多い
➡体力が落ちた高齢者は、インフル・コロナ両方怖い
➡コロナ:オミクロン株での咽頭痛・喉頭炎が軽症化している
➡コロナは高熱が出ない方も多く、コロナの自覚なく受診する方が多い
新型コロナは、重症化の徴候はなく、5類以降後 臨床現場ではコロナよりインフル患者の方が、高熱患者が多く子供を中心に入院適応になる場合があります。
コロナは、咽頭痛が強く発熱がない患者が多いため、自分がコロナの自覚なく受診される場合を多く認めます。
当院は耳鼻咽喉科クリニックため、若年者から比較的若い方の受診が多く、また比較的元気な高齢者の受診が多いためか、2023年以降コロナで入院になる方はいません。オミクロン前半期のようなひどいコロナ喉頭炎や喉頭蓋炎(緊急入院する疾患)を診察することはなくなりました。
◆子供の急性脳症の変化
➡ 急性脳症もコロナよりインフルが多い
➡コロナ渦でコロナのオミクロン関連脳症増加するも2023年は減少して代わりに、インフル脳症が最も増加、ヘルペス脳症、ヒトパレコ脳症など増加
急性脳症の8割は15歳未満で、特に5歳未満の乳幼児が50%程度と小児救急3大疾患の一つで、中枢性の後遺障害を残すことを多く認めます。
以前からインフルエンザ脳症が最も多く コロナ渦では逆に脳症が減少して2022年のオミクロン関連の脳症が増加していました。2023年のコロナ5類以降後コロナ関連脳症は減少するもインフルや他の感染症の流行ともに、インフル脳症が最も多くなりその他にはヘルペス脳症、ヒトパレコウイルスによる脳症が増加しています。
◆コロナ5類以降後は、『風邪は万病の元』の考えが重要
コロナ5類以降後は、当院耳鼻咽喉科の緊急入院は コロナ以外の患者がほとんどです。
現在の怖い病状は、通常の風邪症状から、その本人の睡眠不足、不摂生、疲れ、ストレス、または糖尿病などの生活習慣病の問題もあり、体力・免疫が落ちこじらせ、大病となった状態です。
昔から『風邪は万病の元』と言われることが、コロナ5類以降の感染症の重症化の流れと似ています。
2000年ほど前の、中国の医学書の黄帝内経に『風者百病之長也』(風邪は万病の元の意味)昔の中国では外からの悪い物が入ってくると様々な病気を引き起こすと考えられていました。現代も風邪ウイルス・細菌・コロナ・インフルがやってくると様々な病気を引き起こします。昔は栄養状態が問題だったと思われますが、飽食の時代の現代は生活習慣病・ストレス・不眠・疲れなど現代特有の内面的な要素による免疫の低下が問題です。
いつも言われることですが、十分な睡眠、適度な運動、バランス良い食事と手洗い・換気・必要時のマスク、それにワクチン接種が重症化予防の最も大事なことです。最近のコロナワクチンの接種率は、高齢者50% 全体で20%のようで以前の80%以上だった時からかなり低下しています。今後、無料でなくなればもっと低下すことが予測されます。
スギ花粉症の低年齢化
2019年では、子供5~9歳のスギ花粉症有病率は、20年前の4倍増加 全国平均では約30%。成人では約50%弱。
◆スギ花粉の20年間の年齢別増加率
有病率の比較:年齢層別・20年間隔の比較
*子供(5~9歳)2019年30.1% 20年前の4倍 小学生の増加率が顕著
*年長・思春期(10~19歳)2019年49.5% 20年前の2.5倍
最も多い年齢層(中高生)
*成人(20~59歳)2019年45~48% 20年前の約2倍
*中高年(60~60歳)2019年36.9% 20年前の3.5倍
*高齢者(70歳~)2019年20.5% 20年前の約4倍 高齢化による増加
『コメント』
スギ花粉症は、20年前は20%程度の成人の有病率でしたが、2019年の成人では約50%弱となっています。学童の増加が顕著で、中高年から高齢者の増加率も多くなっています。中年以降の増加はより若い年齢で発症した人たちの加齢による移行と思われます。増加の主体はより若い世代にあります。
鹿児島の場合、2019年で、有病率は18.2%程度で、全国の中でも少ない県になっています。
学童から思春期および若い世代の増加に抑制をかけないと今後もっと増加すると思われます。スギ花粉症の自然寛解率は12%程度(10年間:20-40歳)と低い報告ですので本質的な対応が早急に必要とされています。
『なぜ増加?』
◆乳幼児からの皮膚感作
スギ花粉症もアトピーや食物アレルギーが増加しているのと相関
アレルギーマーチの流れで発症 乳幼児からのスキンケアが重要です。
アレルギーマーチの予防と対策:当院HPを参照
乳児湿疹・アトピー性皮膚炎➡食物アレルギー➡気管支喘息・アレルギー性鼻炎・結膜炎の順に成長につれて発症し、アトピー性皮膚炎・乳児湿疹がアレルギーマーチの出発点であるとされています。
アトピー性皮膚炎の1/3に気管支喘息を発症、1/2にアレルギーマーチが続発すると考えられています。アトピー性皮膚炎があると、アレルギー性鼻炎2~3倍、喘息2~3倍、食物アレルギー6倍のリスクがあります。
アトピー性皮膚炎の乳幼児早期発症、重症・持続性やアレルギー疾患の家族歴があるとアレルギーマーチが発症しやすくなります。
近年小児のアレルギー疾患が増加する中で、この『アレルギーマーチ』の発症、進展を予防することが重要な課題となっています。
➡ダニ対策
アレルギーの原因となるアレルゲンが、乳児期から幼児期にかけて、食物からダニやハウスダストなどに変化していくとされています。そのため、ダニ対策を中心とした環境整備を行うことが、アレルギーマーチの予防につながる可能性があります。
➡腸内環境の改善
科学的根拠はまだ、不十分な領域ですが、一般的には、ヨーグルトなど腸内環境を整えるとアレルギーなど色々な病気の予防や改善につながるのではと期待されています。
科学的にはビフィズス菌が産生する酢酸は酪酸生産菌の栄養源となり腸内の酪酸生成を促します。酪酸は制御性T細胞の活性を促進してアレルギーを抑制すると考えられています。実際、アトピー性皮膚炎の予防・改善目的で、ヨーグルト、オリゴ糖など使用されています。以下に述べる衛生仮説との関連していますが、幼少期の感染症ではない外来微生物にさらされると消化管粘膜の制御性T細胞が活性されアレルギー症状における免疫寛容(アレルギー反応をおこしにくくすること)および抗炎症の役割を担っているという考えがあります。
◆鼻腔粘膜・気道感作
アレルギー性鼻炎 喘息など半分以上はアトピー性皮膚炎や乳児湿疹が無くても発症しています。鼻・気道粘膜からの感作が考えられます。スギ花粉飛散の直接の回避が重要。
若年からスギ飛散にさらされるとスギ花粉症のリスク高まります。春生まれの赤ちゃんは花粉症発症リスク高くなります。
学童では、スギ花粉症シーズンのマスク着用で、スギ花粉症発症率低下が、最近報告されています。低年齢から、スギに暴露されるとスギ花粉症になりやすいことがわかります
◆衛生仮説
先進国では、微生物や寄生虫がいなくなり免疫のバランスが乱れ、アレルギーの増加、自己免疫疾患が増加しています。
米国の農耕民族のアーミッシュは、アレルギーの発症は1/10。年長児から、鼻水など感染源の微生物などをもらうことが多い末っ子はアレルギーが少ない。
外国の大規模調査(2019年)の結果、1歳前に家畜小屋に出入りして、搾りたての生乳を飲んだ子供はアレルギーの発症が有意に少ないことがわかりました。1歳以降の同様の体験ではアレルギー発症の予防効果は弱くなるようです。
家でのゲーム、タブレット鑑賞より、幼少時からの外遊び 土いじり、田舎での生活も必要です。
◆抗生剤の頻回使用や帝王切開は喘息のリスクと関連
2歳までに抗菌薬を使用したことがある児は、5歳時の気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎といったアレルギー疾患のリスクが高まることが分かりました。一般的な風邪のほとんどはウイルス感染であり、抗菌薬は効果がないことからも、不要な抗菌薬の使用は避ける必要があります。
感染対策で手洗いしてもアレルギーが増えるわけではありません。し過ぎると手荒れの原因にはなりますので、皮膚感さによるアレルギーの原因の可能性はあります。手洗いのし過ぎはよくない
👉 どうしたらよいのか
*スギ舌下免疫療法で体質改善(スギ花粉症自然寛解率12%程度 少ない)
舌下免疫療法(スギ、ダニ)当院HPを参照
*スギ飛散シーズン中は、スギに暴露されない生活を送る マスク着用も一つの選択肢
マスクで発症予防:小学生スギ花粉症:当院HP
*若年からスギ飛散に遭遇しない生活をする
*幼少時からのスキンケア
*継続した外遊び、乳児期から農家の生活も体験
*不要な抗菌薬使用控える
*腸内環境の改善:オリゴ糖、ヨーグルトなど食べる
など総合的な対応が必要です。
2024年春スギ花粉症はどうしたらよいの? 鹿児島
舌下免疫療法など体質改善は数年以上かかるため間に合いません。
免疫療法の希望者はスギ花粉が終了してから開始します。飛散中に開始すると副反応が強く出る可能性があるためです。現在、維持量で継続中の方はこのまま継続して問題ありません。
➡まず気象庁などの飛散開始日を確認しましょう。
気象庁のHPによると
鹿児島市は、2月中旬ごろが飛散開始日となっています。鹿児島の北部から北の九州方面はは2月上旬です。
今年はエルニーニュ現象の影響もあり暖冬の冬になりそうです。
奄美の桜の開花が例年より3日早くなっています。今年の冬は1月17日現在、例年より平均2.5度高いようです。
暖冬であれば、予想より少し早く飛散開始の可能性がありますので、早めの準備が必要です。
➡初期療法を考えましょう 当院HP『早くから始めるスギ花粉症治療;初期療法』を参照
スギ花粉症の方の1/3程度は飛散開始日前に軽い症状を感じています。
*通常は、飛散開始予測日の1週間ほどから服薬など開始します。
*または飛散開始前後で症状を感じてすぐに開始します。
➡スギ花粉の回避策や回避行動を行います
めがね、マスク着用、花粉が飛びやすい時間帯の外での行動を控えること
【花粉飛散情報の要注意日】
1:天気が晴れまたは曇り
2:最高気温が高い
3:湿度が低い
4:やや強い南風が吹き、その後北風に変化したとき
5:前日が雨
以上から、前日または当日の未明まで雨で、その後天気が急に回復して晴れ、南風が吹いて気温が高くなる日が要注意日となります。
1日のうち飛散の多い時間帯:正午~3時頃 夕方(地域によって差があります)の外出をなるべく控えましょう。外出しやすい時間帯は8時PM~10時AMごろとなり 外活動は午前に済ませます。 洗濯の外干しは控えます。
➡スギ花粉飛散情報が重要となります
九州地区のスギ、ヒノキ花粉 手間がかかる従来の方法で測定 信頼性が高いデータです。週末は休みです。
週刊予報 PM2.5 天気などと総合的に判断できる情報満載。
ポールンロボによる機械で測定するためリアルタイムで情報提供 当日のWeb症状アンケートも記載されます。
➡鹿児島での例年の花粉飛散の動きを把握します。
鹿児島は関東圏など比較すると、飛散が早く減少する県です。
2019年の全国調査では、鹿児島県のスギ花粉有病率は約20%程度、東京等の関東圏では約50%程度ですので全国的に患者数は、かなり少ない県になります。もっと少ない県は、スギ花粉がほとんどない、沖縄、北海道および奄美などです。
鹿児島のスギ花粉症だけの影響は、例年2月中旬から3月中旬ごろまでで、3月中旬以降はヒノキ花粉に少しずつ移行します。
約一ヶ月程度つらい時期ですが、関東圏では2か月程度つらい時期を覚悟しなければならないようです。鹿児島の場合、飛散開始後7~10日頃に花粉飛散のピーク(本格飛散)を迎え、このピークが2-3週持続して少しずつ減少していきます。
ピークになると、初期療法で行った治療では効果が期待できない方が増えますので、専門医での治療が必要になります。
当院クリニックでは、例年は特に2月下旬から3月上旬は、スギ花粉症の患者さんで、特に込み合います。外で活動が多い方や、鹿児島県外や関東圏などに行かれる方は症状が強く持続も長くなるので特別注意が必要です。
➡3月になりスギ花粉症の後半は、通常の花粉症症状以外にも注意が必要!!
副鼻腔炎、咳、喘息、皮膚炎など合併して幅広い対応が必要になる方が増えます。
スギ花粉症が長くなると、くしゃみ、鼻水、鼻閉、目の痒みのような典型的な症状以外の病状が出現してきます。
鼻副鼻腔炎の合併、咳や痰の増加、咳喘息・喘息が悪化する方が増えてきて、花粉がつきやすい目の周囲や顔に花粉皮膚炎も発症しやすくなってきます。
合併症が増えてくれば、単純に、スギ花粉症の治療を行っても効果は期待できません。
鼻副鼻腔炎の治療、喘息に準じる治療、アトピー性皮膚炎に準じる治療が必要になってきます。眼・鼻・のど・呼吸器・皮膚それぞれ臓器別に治療を行うのではなく、アレルギー全般および上下気道のアレルギーとしてとらえ治療を行い、感染症の合併も考えなければなりません。
めまいの原因は複雑・混在:どう対応?
6月の梅雨のシーズンになれば、なぜかめまいの患者さんが増えてきます。東洋医学では、水毒、水滞と言ってめまい・ふらつきと関連すると考えれています。
西洋医学で、水毒、水滞は内リンパ水腫に近い病態です。具体的例として、比較的に稀なメニエール病、遅発性内リンパ水腫と若い女性に多い低音障害感音性難聴です。神経痛、頭痛などのように気象病としてめまい・耳鳴りも含まれ、低気圧の接近で、副鼻腔・鼓室内圧の相対的上昇の関与が推測されています。
『めまいへの初期療法としての対症療法』
めまいの薬物治療は何十年も前から変わっていません。ぐるぐる回るめまいであれば、吐き気も強く、点滴で、吐き気止め、脱水対策を行い、内服は吐き気止めのナウゼリン、トラベルミン、漢方など処方されることがよく行われます。但し原因を考えてではなく、とりあえず症状を緩和するため、対症療法として対応されます。この中には脳からのめまいも混ざっている可能性があります。めまい・吐き気・嘔吐は自然治癒することも多くある為そのまま落ち着き、浮遊感や吐き気はしばらく持続することは、よく経験する経過です。その後、めまいが反復または持続することもありますので、原因により判断しての対応が必要になります。
原因療法の必要性 ➡ 耳鼻咽喉科・脳外科・神経内科などで精査を行い、疾患を見極めて対症療法から原因療法に変えなければいけません。
『対症療法は最小限で!!』
身近な対症療法の例として、風邪の時には、風邪薬として症状をとりあえず抑える目的で最小限処方され、1~2週間自然治癒するのを待ちます。原因療法ではありません。発熱の時は、解熱剤を使用します。しかし発熱は病原への免疫反応を高める効果があるため解熱剤で下げ過ぎると弊害の方が大きくなることがあります。風邪薬は、眠気や倦怠感、のどが渇き、痰の切れや便の出が悪くなったりすることも多くあります。高齢者が咳止めを続けると肺炎のリスクが増加します。
対症療法に依存するのはよくありません。
『複雑・混在するめまい疾患の原因療法:どう対応?』
めまいの原因は、以下に示すように、あまりにも多く見極めるのがたいへんです!!
大きく分けて、①耳から ②脳から ③身体・心身からかを考えます。
👉 疾患のリスクと疾患の頻度から、次の2点の確認をまず考えましょう。
➡5%未満の稀な脳からの危険なめまいの原因を見逃さない事。高齢者や糖尿病、高血圧、心疾患があれば病院や脳外科にて脳の画像検査が必要です。
➡頻度としてめまいの半数近くを占める良性発作性頭位めまい(BPPV)かどうかの見極めが最も重要です。耳鼻咽喉科専門医またはめまい相談医を受診することです。
👉 その他の一般的な注意点は?
➡梅雨前から夏は、熱中症の初期症状としてのめまい・ふらつきを忘れないように!!
➡高血圧薬や睡眠薬・精神薬など服用している方は、薬剤性めまい・ふらつきではないか担当医と相談しましょう。
①耳から
前庭神経炎
めまい伴う突発性難聴
外リンパろう
②耳・内耳の症状だが脳の関与
前庭発作症
小児良性発作性めまい症(幼児に多い BPPVとは違う 片頭痛と関連)
明らかな脳の関与
一過性脳虚血発作
椎骨脳底動脈循環不全
神経変性疾患
脳腫瘍
➂身体・心身から
頸性めまい
心因性めまい
薬剤性めまい
貧血
循環器疾患
サルコペニア フレイル(加齢性前庭障害と合併)
『良性発作性頭位めまい(BPPV)にはさらに細かい原因が分類されます』
最も頻度が高い良性発作性頭位めまい(BPPV)には、耳石に位置により原因が異なります。
*後半器官結石 *外側半規管結石 *外側半規管クプラ結石
原因により治療法は少しずつ異なります。前庭リハや耳石置換療法のやり方を変えて対応します。
『反復するめまいの原因は時間とともに変化していき、複雑混在するようになります』
*最初は通常のめまい疾患で発症しても、めまいは反復することが多く、めまいに対する予期不安が出現し、不眠が出現し外に出るのが怖くなり心因性めまいを併発しやすくなります。また運動不足から、BPPVも出現する可能性が高くなり、めまいの原因が複雑化してきます。
*メニエール病・めまいを伴う突発性難聴・HUNT症候群の場合、めまい以外に難聴・耳鳴りも持続するため、精神的負担が大きく、うつ傾向も併発して心療内科受診する方もいます。
*強いめまい発作が持続する前庭神経炎は、めまい・ふらつきの持続は長期化することが多く、その後、運動不足等からくるBPPVが途中出現することがあります。
*ストレスなどが誘因となり、まじめな方に多いとされるメニエール病は働き盛りの方に多く、めまいが反復する疾患です。この疾患にもBPPVが混在することがよくあります。
*メニエール病は、更年期年齢および前後の女性に多く、女性に多い疾患である片頭痛も持っている方は片頭痛関連めまい(前庭性片頭痛)や更年期による自律神経によるふらつきなどが混在することもあります。
*2017年以降に国際的に統一された慢性機能性めまいのPPPDは、先行する通常のめまい疾患や、パニック発作・不安の平衡障害後、先行する疾患の病態が無くなり、3ヶ月以上ほとんど毎日持続する浮遊感・不安定感が生じる疾患です。先行するめまい疾患が混在していることもあります。先行するめまい疾患から3ヶ月以上経過して疾患が判断できるようになりますが、特異的検査がないため診断がつきにくく治療にも難渋する疾患です。
👉このようにめまい疾患は、反復するにつれ数週間~数ヶ月と時間経過ともに別のめまい疾患が併発し混在することが多くなります。
『複雑・混在するめまい疾患に対応するため、めまい相談医の役割』
日本めまい平衡医学会では2011年にめまい相談医制度を発足しています。
めまい臨床の専門的知識と高度の診療技術をもつ会員を対象に講習会と試験を受け合格者を認定する制度です。(鹿児島県では、現在6名:2023年6月6日)複雑極まりないめまい疾患に対応するには、『耳』『脳』『身体・心身』なのか判断できる総合的な臨床能力が必要になります。脳・身体・心身からの可能性の場合、該当する専門医や総合病院への紹介が必要になります。
乳幼児の病気は鼻から!!
『赤ちゃんの鼻呼吸の重要性』
生まれたばかりの赤ちゃんは、口呼吸がうまくできず鼻が詰まると母乳やミルクが飲めず大変です。新生児は周囲がぼんやりとしか見えていません。お母さんの匂いを頼りに母乳を求めていきますので、赤ちゃんの鼻呼吸は生命線とも言えます。薬の効果が期待できないことが多く専門医での処置も必要になります。
『乳幼児の風邪症状』
乳幼児の時期は、よく風邪をひきます。ぐったり感が強い、呼吸苦がある、顔色が悪いは緊急性がある兆候です。
通常は風邪をひいても鼻風邪程度で熱は1~3日程度持続し、元気はあります。鼻水、鼻閉、咳、痰は1~2週間ほど持続して自然治癒することがほとんどです。但しこの年齢では、風邪をひきやすく何度も同じような症状を反復します。風邪をひいても、うまく病気と付き合えば免疫力がついてお子さんの自然治癒力は高まり自分で乗り越えることが出来るようになります。
『鼻と子供の病気』
中耳炎、目ヤニ、ゼーゼー、持続する咳痰、いびき、無呼吸、口呼吸、咽頭扁桃炎と併発する発熱は、鼻と関連して起こすことが多い疾患や症状です。
鼻の奥には、中耳とつながる耳管(上咽頭に開口)、目とつながる鼻涙管(下鼻道に開口)が鼻へ開口しているため、鼻の炎症や菌・ウイルスが中耳や眼に波及していきます。
鼻副鼻腔炎の鼻汁は鼻の奥から後鼻漏として咽喉頭へ流れ込み、咳・痰・ゼーゼーが出てきます。また上気道が悪いと下気道の気管・気管支・肺にも影響が及ぶため、ゼーゼーや治りにくい咳痰が持続し、肺炎も併発することもあります。
鼻の奥の上咽頭粘膜の腫脹(アデノイド肥大)は生理現象として3~6歳ごろは大きくなるため、通常の鼻炎をおこすだけで、いびき、無呼吸、口呼吸が夜間になると顕著になります(睡眠時無呼吸症)。口呼吸があれば、のどからの発熱が起こしやすくなります。
子供の睡眠時無呼吸症は、夜間の症状の他には、昼間の傾眠は少なく、多動、体重増加不良、おねしょなど大人と違う症状が出現してきます。
➡感染源は?
パパ、ママ、兄弟姉妹、保育園、幼稚園からもらう事がほとんどですので、家族も同時に治療を行い、集団生活を少し休めば治りも早くなります。
➡診断は? 子供さんは動くので容易ではありません
採血では全身の炎症反応や肝臓・腎臓などの臓器の異常は確認できても、耳、鼻、のど、喉頭、上咽頭アデノイドの状態は、局所を直接見て確認しないとわかりません。子どもの場合は協力が難しく診断は容易ではありません。レントゲンなど画像検査は動くため大人のようにはできません。
上咽頭アデノイドや喉頭の確認は、抑制してのファイバースコープが必要になることもあります。中耳の確認も耳垢除去を顕微鏡下に行なわないとわからないとこともよくあります。じっとしてくれないので多人数で抑制して行うこともあります。全身状態、顔色、声の状態、喉頭、肺の音も確認が必要です。
鼻の吸引処置を行うと同時には鼻水の性状や鼻の粘膜の状態を確認します。鼻粘膜が腫れて悪いのか、鼻汁貯留が問題なのか、水様、膿性、粘調な鼻汁かを確認すると薬の選択の参考になります。
➡お子さんの病気が治りにくいときに、鼻関連では次のことを考えます!!コラムも参考に
コラム ①鼻と子供の中耳炎 ②お子さんの中耳炎の疑問に答えます
自分から耳痛の訴えは2歳ごろまでは難しく、機嫌が悪い、耳に手がいく、目ヤニなど参考にします。
*咳痰が持続するとき➡鼻副鼻腔炎の合併による後鼻漏
*ゼーゼー咳痰が治らないとき➡アレルギー性鼻炎および鼻副鼻腔炎の合併、アトピー体質があることも多い
コラム ①鼻と秋の喘息 ②お子さんの喘鳴は何タイプ
*目ヤニが持続するとき➡鼻副鼻腔炎・中耳炎の合併
*いびき・無呼吸・口呼吸・夜間体動・おねしょ➡鼻副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、上咽頭炎、アデノイド扁桃肥大の合併 
コラム 睡眠時無呼吸症候群(OSAS)
*よく風邪をひき、熱を出す➡口呼吸があり、鼻副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎・アデノイド扁桃肥大の合併
➡治療は?
薬や処置・鼻洗が通常行われます。保存的治療で改善悪い時、鼓膜切開や病院でのアデノイド切除や扁桃摘出、鼓膜チューブ挿入など行うことがあります。
👉 耳・はな・のどの専門医である耳鼻咽喉科では、耳・はな・のどの奥を見てしっかり診断を行い、治療を考え、必要な場合は奥の画像や動画を用いて説明を行っています。
« Older Entries