院長の健康情報コラム
2018年花粉症予想(スギ+ヒノキ)
気象庁から2017年10月3日、2018年のスギ・ヒノキ花粉症予想が公表されました。
スギの花芽は、7月から細胞が分化しはじめ、10月頃にかけて成長します。
その為、花粉の飛散量は前年夏の気象条件が大きく影響します。
気温が高く、日照時間が多く、雨の少ない夏は花芽が多く形成され、翌春の花粉の飛散量が多くなるといわれています。
2017年の夏は、全国的に気温が高く、日照時間も多くなりました。
東北・関東・甲信・四国地方は前年の1.5倍以上の飛散量となり、
九州特に鹿児島は、前年より少なくなるようです。宮崎は前年より増加します。
今年の九州の夏は気温が高く、日照時間が長く、雨が少なかったのに
飛散量が少なくなる理由がわかりませんが、花粉症の方には朗報です。
2018年春の花粉飛散予測 -日本気象協会- http://tenki.jp/pollen
予防接種と間違い
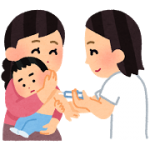 近年の予防接種法の改正により、複数のワクチンが定期接種に導入され、ワクチンギャップは解消されつつあります。
近年の予防接種法の改正により、複数のワクチンが定期接種に導入され、ワクチンギャップは解消されつつあります。
一方で小児における定期の予防接種は、とくに乳幼児期に接種が集中しており、
また、ワクチンの種類によって接種間隔や接種回数が異なっていることなどから、
ときに予防接種に関する間違い(誤接種)が生じる可能性があります。
厚労省は、昨年度の『間違い』の公表を行い、前年度より434件増の6602件の報告が
ありました。半分は接種間隔の間違いで、他には対象年齢外接種、不必要な接種、
対象者を誤認、摂取量の間違い、期限切れワクチン接種などの順でした。
特に、小児科でのワクチンは種類が多く、それぞれ細かい対応が必要なため、
こういった間違いが生じていると思われます。
当院は、インフルエンザワクチンと成人肺炎球菌ワクチンしか行っていません。
常に二重チェックを行い、スタッフ共々、気を引き締め行いたいと思います。
月見と蜂
9月11日愛媛で車いすの老婦人が、デイサービスの帰り、多数の蜂に刺され死亡する痛ましい出来事が起きました。
日本の蜂は、夜は活動を休止する習性があり、ハチの巣の駆除も日没後行うそうです。
活動が低下する日没後の秋の月見は安心して出かけられます。
10月7日の吉野公園にて、日没後、月見コンサートが盛大行われ、最後の沖縄太鼓は、踊れて楽しめました。
その後1週間以上過ぎ、肌寒くしばらく秋雨が続きます。
スズメバチなどは、気温が低い日や、雨の日は活動が低下するようです。
健康情報コラム始めました。
「院長の健康情報コラム」として、健康に関する身近な話題を取り上げていきたいと思います。
Newer Entries »

