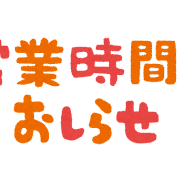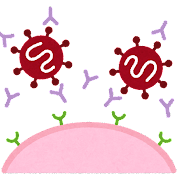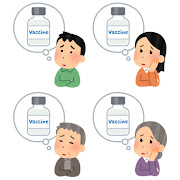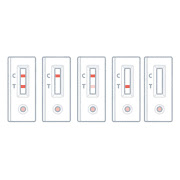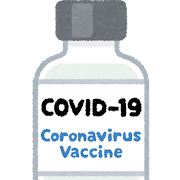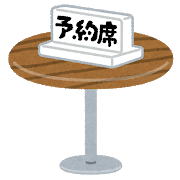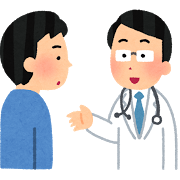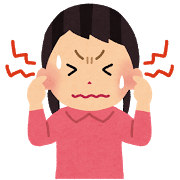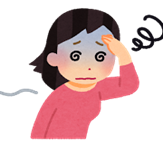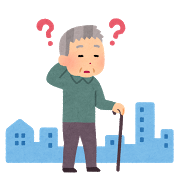お知らせ
8月の休診(21日)&お盆休み(11~15日)
【8月の休み 及び お盆休みは以下のようになります】
8月11日(日曜)12日(休日)山の日 振替
8月13日~15日 休診 お盆
8月16日(金曜日)通常診療
8月21日(水曜日)休診
受付時間変更(Webも):終わりが15分早くなりました!
2024年2月から
受付時間を診療時間の15分前までといたします。Web受付も15分早くなります。・
午前 窓口受付8:30~11:45 Web 8:45~11:15 月~土曜
午後 窓口受付14:30~17:45 Web 14:45~17:15 月火木金
診療時間 月~土曜 8:30~12:00 月火木金 14:30~18:00
Web受付された方は,
午前11:45、午後17:45以降は、自分の順番が呼ばれたときに不在の場合はキャンセル扱いとなります。
コロナ重症化リスク抑制指標:抗体測定(定量)行います。
当院では、新型コロナウイルスワクチン接種後の中和抗体の確認(採血)を、自費になりますが行っています。ご希望の方はお問合せ下さい。
中和抗体は、新型コロナ感染による重症化予防の判断指標の一つとなります。
産経新聞記事:3回目接種で抗体価36倍 (2022年1月21日)
2022年1月23日現在、オミクロンの爆発的感染広がっているところです。鹿児島では2月から3回目の新型コロナ接種が始まります。
『対象者』
*1~2回目接種で、副反応が強く3回目接種をするのか迷っている方
*3回目接種後の抗体が上昇しているか不安な方(接種後3週間以降に測定)
免疫抑制薬やステロイド服用者や高齢者では抗体が上がりにくいことがあります。
*自分の中和抗体に関心がある方 等が対象者になるかと思います。
一般に普及しているコロナ定性検査 IgG、IgMキット(約500円~2000円程度 ネット販売価格)は、過去に新型コロナに感染したかのN抗体を主に測定しますのでワクチンの効果判定の指標の中和抗体にはなりません。N抗体価はすぐに低下します。また測定の信頼性に問題があることも指摘されています。
➡ 2020年6月東大先端研の報告では、抗体定性検査陽性の9割は定量検査では陰性の報告があります。
➡ S抗体はスパイクタンパク質への抗体で、ワクチンの標的であるウイルスの増殖を抑制する中和抗体です。N抗体と違い寿命が長く長期に測定可能です。
➡ N抗体は炎症を起こす病変悪化に関係します。
👉 コロナワクチン後の効果判定としての中和抗体は、定量精密のS抗体の測定が必要になります。
◆費用 自費 (4500円 税込)
◆委託先で米国医療機器大手アボット社定量検査使用(Abbott)
◆結果判明日数7日
当院のよくある質問集
【受付編】
*クレジットカード・電子マネーは使えますか?
*車いすは大丈夫ですか?
*おむつ交換はできますか?
*予防接種はできますか?
*親御さんが診察時、子供(乳幼児)の面倒はみてもらえますか?
*保険証が無くても受診できますか?
*妊婦ですが大丈夫でしょうか?
*病院嫌いの子供ですが、大丈夫でしょうか?
【診察編】
*赤ちゃんをみてもらえますか?
*頻回な通院が必要ですか?
*鼓膜切開は、すぐにするのでしょうか?
*中耳炎でプールはいつからできますか?
*耳垢除去だけで受診できますか?
*咳がひどいのですが、みてもらえますか?
*補聴器の購入は可能でしょうか?
*耳鳴りは治るものでしょうか?
*めまい・ふらつきは耳鼻咽喉科でみてもらえますか?
*いびき・睡眠の無呼吸は耳鼻咽喉科でみてもらえますか?
*喘息はみてもらえますか?
*食物負荷テストはできますか?
*アトピー性皮膚炎はみてもらえますか?
*アレルギーの体質改善はできますか?
*嚥下障害の検査はできますか?
*西洋薬より漢方薬の治療を希望していますができますか?
【受付編】
できます。順番予約(WebではLINEにも対応)となります。朝は8:45~11:30昼は14:45~17:30にWeb順番予約をしています。
詳細は
➡チェックオン(当院サイト)で確認してください。
早朝から来院順番予約は、クリニック風除室(平日8:00 土曜6:30頃開きます)の記載簿に書けるようにしています。詳細は当院HPで確認下さい。
➡ご来院の皆様・アクセス(当院HP)開院が8時頃、診療は8:30開始です。
今のところ使用できません。
大丈夫です。バリアフリーで一階のみの診療フロアです。土足のまま入室できます。
当院にも車いすの準備はしていますので、必要な場合は前もって電話連絡お願いいたします。
女子トイレ室におむつ交換テーブルがあります。便やおむつは、感染の原因にもなりますので持ち帰りをお願いしています。袋が必要な方は受付にお尋ねください。
できます。次のサイトで確認して下さい。
➡定期予防接種(原則5歳以上)(当院疾患予防)
➡無料成人男性風疹検査・ワクチン接種(当院疾患予防)
➡妊娠を希望する女性その家族の無料風疹抗体検査、高齢者肺炎球菌予防接種助成(当院疾患予防)
インフルエンザワクチン(10月~1月中旬)やおたふくワクチンは1歳以上で行っています。5歳未満の定期予防接種は小児科でお願いしています。小児科のような予防接種の時間枠はありませんが、通常診療時間内に行っています。前もって電話での予約をお願いいたします。
*親御さんが診察時、子供(乳幼児)の面倒はみてもらえますか?
混雑時以外であれば当院スタッフが対応いたします。
*保険証が無くても受診できますか?
できますが自費診療となります。保険証作成後、保険診療分の返金ができることもあります。詳細は受付でご確認お願いいたします。
問題ありません。
➡妊婦&授乳と薬:飲んで大丈夫?(当院コラム)も参考にしてください。
*病院嫌いの子供ですが、大丈夫でしょうか?
子供さんが嫌がることを確認して、できる範囲で対応いたします。前もって情報提供をお願いいたします。
【診察編】
問題ありません。風邪症状は、通常は鼻水、鼻閉、咽頭痛、発熱、悪寒、頭痛が先行して、食欲低下、咳、痰などが持続します。乳幼児は耳痛や、ゼーゼーが持続することもあります。お腹の風邪では、嘔吐、発熱、下痢が出現することが通常です。
当院では、耳、鼻、上咽頭、口腔、扁桃、喉頭の上気道と頸部に加え、下気道、肺も含めを、診察を行っています。耳・上咽頭・喉頭やのどの奥は内科や小児科で対応が難しい領域です。お腹のかぜも初期対応はおこなっています。
➡かぜ症候群(当院HP)
➡咳(当院HP)
➡のどの違和感・咽頭痛・頸部の腫れ(当院HP)
➡風邪・インフル予防の基本!!(当院コラム)
➡風邪対応と色々な感染症(当院疾患案内)
を参考にしてください。
問題ありません。生後数週間から、鼻閉、鼻汁、外耳や中耳、のどのトラブル、耳垢などご相談下さい。発熱、咳の3ヶ月未満の赤ちゃんは小児科専門医受診も同時にお願いします。
赤ちゃんは、口呼吸がうまくできず鼻呼吸に頼っています。鼻がつまるとミルクや母乳が息苦しくて飲めず、うまく呼吸が出来ず機嫌がわるくなります。お母さんにとっては一大事です!!
小児科に相談して薬や自宅鼻吸い指導を受けてもうまくいかないことが多くあります。生後5~6ヶ月頃から鼻炎に伴い中耳炎も起こしやすくなります。自宅鼻吸いしても鼻の奥の上咽頭の炎症や多量の鼻汁まで改善しません。上咽頭に炎症・感染がおきると耳管咽頭口を通って中耳炎をおこしてしまいます。上咽頭(鼻の奥)を含めた鼻汁、鼻閉、中耳炎の対応をできるのは耳鼻咽喉科になります。
➡鼻と子供の中耳炎(当院コラム)
➡急性中耳炎の治療の変化:治療から予防へ(当院コラム)
も参考にしてください。
*頻回な通院が必要ですか?
各個人で違います。耳鼻咽喉科は頻回な通院のイメージがあります。当院では急性期や重度の方は頻回な通院をお願いすることがあります。鼻かみが出来ない赤ちゃんやお子さんは鼻処置を含め、まめな通院が必要なことがあります。当院では通院が少なくなるように、ご自宅での点鼻や鼻洗などの在宅治療も指導しています。
H27年の全国の1件当たりの月の全科の外来受診日数の平均は1.58日、14歳以下は1.47日、75歳以上は1.84日のようです。耳鼻咽喉科1.6日、整形外科2.8日、小児科1.51日、内科1.47日、整形外科が突出しています(中医協)。当院は、月に平均1.35日程度ですので、通院が少ないクリニックになります。
すぐに行うことはありません。最近は、ワクチン効果による軽症化や多様な抗生剤のおかげで鼓膜切開をする回数は激減しています。鼓膜切開は、お子さんにとってストレスにもなり、必要な場合は説明と了解の上で行います。
➡急性中耳炎の治療の変化:治療から予防へ(当院コラム)を参考にして下さい。
問題ありません。耳垢栓塞症として保険診療で、対応できます。耳垢除去の必要性をまず説明の上ですすめていきます。
耳掃除の必要性について次のコラムを参考にしてください。
➡耳掃除は必要か?外耳炎・かび・事故(当院コラム)
急性中耳炎(耳痛、発熱、鼓膜発赤などあり)は、急性期と耳漏が多量の場合は禁止です。最低1~2週間は禁止になることが多いと思います。
詳細は
➡プールに入ってよいですか?耳・鼻の病気(当院コラム)を参考にしてください。
問題ありません。お子さんから高齢者まで対応しています。鼻・のど・気管支・肺からなのか感染症・アレルギー・嚥下機能低下・心不全・胃食道逆流症などの関係はないかなど確認しながら対応していきます。
➡かぜ症候群(当院HP)
➡咳(当院HP)
➡増え続ける咳の患者さんたち(当院コラム)
➡鼻と秋の喘息(当院コラム)
➡胃酸の逆流と耳・鼻・のど・呼吸器(当院コラム)
➡自宅でできる誤嚥性肺炎予防(当院コラム)
を参考にしてください。
肺癌・結核・肺線維症・心不全を疑う場合や、ぐったり感が強いお子さん、高度な低酸素・重度の喘息・肺炎・COPDが考えられるときは総合病院や呼吸器内科、稀に循環器内科紹介となります。精査に胸部・頸部のCT・MRIが必要な場合も病院紹介となります。
購入可能です。当院の院長は補聴器相談医(日本耳鼻咽喉科学会)を取得していて、認定補聴器専門店(サイト)の補聴器認定技能者の専門の方と当院で補聴器外来を行っています。まずは受診の上での、予約制となります。少しお時間をいただきますが、各種身障など書類作成も問題ありません。
➡補聴器外来(当院HP)で確認して下さい。
イエスandノーです。
急性期の耳鳴りは、中耳炎、突発性難聴など治療で改善の可能性がありますので耳鼻咽喉科受診を早めにしましょう。慢性期(3ヶ月以上)の耳鳴りは、加齢変化や内耳疾患の後遺症、稀な聴神経腫瘍など改善は難しく、今の医学では特効薬的な効果的な薬は無いと考えらえていますが、医学的加療で耳鳴りをやわらげ日常生活に支障を及ぼさないことは可能です。ネットや新聞では、ビジネス先行のサプリなど過大な効果をうたっている情報の氾濫がみられます。
慢性期の耳鳴りの場合、耳鳴りに対する正しい知識と考え方を学ぶことから始めてください。次の当院コラム・HPやサイトが参考になります。
➡自宅でできる耳鳴り対策(当院コラム)
➡耳鳴り音響療法(TRT)のHP(マキチエ)
➡補聴器・耳鳴り音響外来(当院HP)
すぐに治る薬に固執する方や、不眠・心因的に悩みが強い方は、改善が悪くなる傾向があります。
めまい・ふらつき全般に対応しています。
当院院長はめまい相談医(日本めまい平衡医学会)を取得していて以下の要領で行いますので、ご確認お願いいたします。
➡めまい・ふらつき(当院HP)
➡めまい・ふらつきでお悩みの方へ(当院疾患案内)
脳や心疾患の可能性が高いときや高度の貧血の場合は、内科や脳外科紹介となります。
問題ありません。いびき・無呼吸の原因は子供さん場合、鼻疾患・アデノイド肥大・扁桃肥大です。大人の場合は、鼻疾患、肥満、舌根肥大、上中咽頭が狭いことが一般的な原因となります。また顎が小さい方も起こしやすくなります。
これらの原因精査を奥まで観察して行うのは耳鼻咽喉科です。当院の無呼吸検査では、簡易アプノモニター(大きいお子さんと成人)を行っています。
詳細は次のサイトで確認して下さい。
➡睡眠時無呼吸症(OSAS)(当院HP)
➡睡眠時無呼吸症はなぜ起こる?(当院コラム)
➡睡眠時無呼吸症のマスク(CPAP)(当院コラム)
➡睡眠時無呼吸症と間違いやすい睡眠障害(当院コラム)
問題ありません。当院院長はアレルギー専門医(日本アレルギー学会)を取得しています。肺から耳・鼻・のどを含めた『one airway one disease』として対応しています。
次のサイトで確認お願いします。
➡当院のアレルギー対応(当院HP)
➡運動・アスリートと喘息・鼻炎(当院コラム)
➡肥満と喘息:ダイエットで喘息が治る?(当院コラム)
➡鼻と秋の喘息(当院コラム)
➡アレルギーマーチの予防と対策(当院コラム)
➡あなたの喘息は何タイプ?成人編(当院コラム)
➡お子さんは喘鳴(ぜんめい)は何タイプ?(当院コラム)
当院では行っていません。
➡鹿児島県の食物経口負荷試験実施医療機関(鹿児島県医師会サイト)で確認して下さい。
当院のアレルギー対応については次のサイトで確認して下さい。
➡当院のアレルギー対応(当院HP)
対応可能です。鼻炎・喘息の原因となるダニや食物アレルギーの原因となる物質は幼少時期からの皮膚感作が大きく関与しています。鼻炎・喘息は気道感作も関与してきます。
幼少時からの湿疹・アトピー性皮膚炎の治療およびスキンケアは、アレルギーの領域では一丁目一番地です。重度のアトピー性皮膚炎やアトピー性皮膚炎などの皮膚疾患単独の場合は皮膚科または幼少時のお子さんは小児科を勧めています。
次のサイトを参考にしてください。
➡当院のアレルギー対応(当院HP)
➡アレルギーマーチの予防と対策(当院コラム)
➡汗とアトピー、そして漢方(当院コラム)
➡よくわかる子供の漢方:アトピー・蕁麻疹・よだれ皮膚炎・水いぼ(当院コラム)
*アレルギーの体質改善はできますか?
イエスand ノーです。以下の体質改善とアレルギー体質を作らない(未病)ように対応しています。
身体には、外部から侵入してきた異物を体外へ排出して、身体を守るための免疫機能があり、通常は身体に害を与えることは少ないとされています。体質によっては免疫機能が特定の物質に過剰な反応を見せてしまうことがあり、さまざまな弊害を受けてしまうことをアレルギーと呼んでいます。
西洋医学的には、内服・外用・吸入などで、この免疫反応と症状を一時的にコントロールする治療(対症療法)を行います。免疫機能に働きかけて改善する免疫療法(体質改善)は約100年前から行われてきましたが、頻回な通院注射や副作用(アナフィラキシーなど)の問題もあり、あまり普及してきませんでした(皮下免疫療法)。最近、副作用が少なく注射せず自宅加療で、月1回程度クリニックで経過を確認する治療の舌下免疫療法が普及してきています。数年以上治療行いスギ・ダニのアレルギー性鼻炎への効果は70~80%程度で、喘息の一部にも効果があります。しかし、個人差があり全員に効果があるわけではありません。
➡舌下免疫療法(スギ・ダニ)(当院お知らせ)で確認して下さい。
➡自分で行うスギ花粉・鼻炎結膜炎の対策(黄砂・PM2.5を含む)(当院コラム)
幼少時からのアレルギーマーチを防ぎアレルギー体質を作らないため、
- 幼少時期からの皮膚のスキンケアと治療、
- 離乳食を遅らせない、
- 食物除去をし過ぎない
ことにより食物アレルギー予防が試みられています。
➡子供の食物アレルギー(当院HP)で確認できます。
- 不要な抗菌薬の使用を控える(腸内細菌を整える)
- ダニ対策
もアレルギー疾患対策に重要です。
- 幼児期から家畜と触れ合うことも
花粉症、アレルギー性鼻炎、喘息の予防に効果あることが報告されています(衛生仮説)。
➡アレルギーマーチの予防と対策(当院コラム)
➡実践ダニ対策(当院コラム)を参考にしてください。
食生活を整え、腸内細菌を整えることも重要です。
漢方による体質改善は、直接免疫機能に働きかける治療ではありません。
漢方薬や運動・食養生などで冷え、おなかの不調、ストレス、お血、水分代謝、慢性炎症を改善させ、体の偏移を中庸にもどすことを目的とします。未病(検査では異常なく病気が予測される状態)を改善させるため、食養生・生活習慣の改善も行い、漢方薬と併用していきます。腸内細菌もよい方に向かいます。間接的に免疫の過剰を抑えることもあるかもしれませんが、不確実です。
具体的な食養生の例として、脂もの、甘い物を控える。加工食品を避ける。旬なものをできるだけ丸ごと食べる。冷え性の方は、根菜類を食べ、生もの(果物・野菜)や冷たいもの酢の物を控えます。
➡漢方処方(当院HP)
➡漢方処方を希望される方へ(当院疾患案内)
検査はできます。
まず受診の上で、必要な方は検査予約をしていただきます。当院はバリアフリー、一階のみですので車いす・ストレッチャーで診察室入室可能です。
往診での嚥下機能検査は今のところ行っていません。高齢者嚥下障害は、脳疾患後遺症や加齢変化と関係するため画期的に改善させることは難しく、今ある能力を最大限にいかして、リハビリで、できるだけ進行を遅らせることになります。在宅医、歯科医、栄養士、言語聴覚士さんなどパラメディカルの方も含めたチーム医療が原則となります。
➡自宅でできる誤嚥性肺炎予防(当院コラム)
➡ドライマウス・窒息・誤嚥性肺炎(当院疾患案内)
を参考にしてください。
問題ありません。
当院院長は、漢方専門医を取得しています(日本東洋医学会)。当院の方針については次のサイトでご確認お願いします。
➡漢方処方(当院HP)
➡漢方処方を希望される方へ(当院疾患案内)
補聴器・難聴・耳鳴り外来
👉 補聴器&耳鳴り音響療法外来を行っています。
◆難聴でお困りの方は、
難聴の原因を確認の上、治療可能な場合は、治療を優先いたします。改善が難しい場合は、補聴器適応または身障適応の判断を行います。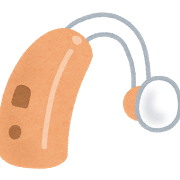
補聴器希望の場合、認定補聴器技能者と院内で補聴器外来(予約制)を行いますので、まずは受診の上、補聴器適応があるか確認してからの予約となります。
☞ 補聴器外来(吉 耳鼻咽喉科アレルギー科HP)
☞ 補聴器と認知症予防について見てほしいサイトは
認知症と耳鼻咽喉科&補聴器(当院コラム)20180102
◆耳鳴りでお悩みの方には、
通常診療の中で、治療またはカウンセリングを行い、難治性の耳鳴りで適応があれば、補聴器使用しての耳鳴り音響療法(TRT)外来を予約していただいています
☞ 補聴器・耳鳴り音響外来受診希望の方は、以下のサイトをご覧ください。
👉 耳鳴りでお悩みの方にまず見てほしいサイトは
« Older Entries