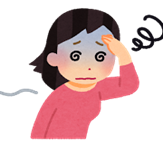鼻と眩暈と熱中症:暑さ対策は大丈夫?
平成から令和への10連休のGWがはじまりました。体を少しずつ暑さに慣らして、夏の熱中症対策を始める時です。
下記の『予防対策』を考えた対応を毎日心がけ、下記の『暑さ指数』を毎日確認してその日の行動を考え、熱中症に遭遇すれば下記の『現場対応』を行います。
環境省の下記のサイトが良くできていますので、まず見てください。
【現場対応】サイト
現場で、意識を確認して、なければ救急車、あれば水が飲めるか試みます。意識があれば、日陰・涼しい場所に移動して、服を緩め、水と塩またはスポーツドリンクをとらせ冷やします。頸部や脇の下を氷嚢,なければ自動販売機の冷えたペットボトル飲料水などで冷やします。
熱中症は、環境、からだ、行動が原因で起こします。
*環境:高温、多湿、風が弱い、エアコン無い部屋、閉め切った部屋、熱波
*からだ:肥満、高齢、小児、脱水、体調不良、糖尿病、心疾患など
*行動:慣れない運動、長時間の屋外作業、水分不足、スポーツ(登山、野球、マラソン、剣道、バレー、バスケットなど)
【暑さ指数:WBGT】サイト(気温、湿度、輻射・日射を考慮した指数)
温度計の指標とは異なります。 暑くなれば毎日確認をしましょう!
👉 熱中症対策で最も重要なことは、①良い汗をかき気化熱で深部体温を下げること、②皮膚からの熱放散が上手にできる事です。
そのためには、脳は熱に弱く脳の体温調整機能を低下させないよう脳の温度を40度前後以上ならないようにしなければいけません。
熱中症には、次の分類があります。
◆労作性熱中症:
若い人に多く、運動や労働と関連し,自宅外で急に発生
高齢者に多く、運動とは関係なく加齢変化と基礎疾患が関連して、徐々に進行して自宅の寝室、リビング、トイレで多く発生, 30度以上ではエアコンの使用が重要となります。若い人の労作性熱中症は、熱中症対策、啓発活動で減少してきていますが、高齢者の非労作性熱中症は近年増加していて、重症度が高く死亡例が多くなっています。
6月になり梅雨明け後急に気温が高くなると熱中症の方が増えてきます。暑熱馴化とは、暑くなっても体温調整がうまくでき、良い汗をかけるように前もってすることです。慣れていない人が、夏の肉体労働を開始すると3日以内の熱中症発生が多いことがわかっていますので、産業医療では、1週間以上まえから、仕事に少しずつ慣らしてから行うようになってきています。
👉 高率よい暑熱馴化の方法
インターバル速歩と運動後のコップ一杯の牛乳で、効率よい暑熱馴化を行います。高齢者ではサルコペニア(筋肉萎縮)対策にもなります。
◆インターバル速歩:
少しきつめの早歩き3分、ゆっくり3分歩行を交互に30分、週に4日以上1~2週間行うと効果が期待できます。若い人は、1週間程度から効果が出るようです。
詳しくは次の環境省youtubeを4分から見てください。環境省:夏を健康に過ごすための体つくり(youtube)
上記運動を5か月持続すれば、筋力増加、体力増加20%、高血圧、糖尿、肥満が20%改善する報告があります。
次の環境省youtubeで詳細が確認できます。環境省:暑さに強い体つくり(youtube)
運動後に糖質とタンパク(牛乳など)を摂取すると体内血漿量とアルブミンが増加して、体温調整能と下肢筋力増加に効果があり、下肢から心臓への循環量の増加が期待できます。末梢血液量の増加による皮膚からの熱放散や脳の体温調整機能低下予防にも役立ちます。日常の水分摂取も、利尿作用があるカフェイン、アルコール飲料は避け、水や麦茶を推奨。
➡ふらつき・めまいと熱中症
1度:熱中症初期 ふらつき・めまい・たちくらみ(脳への一次的な血流不足)
こむら返り・足のつり(脱水によるナトリウム不足)、気分不快、手足のしびれ
2度:頭痛、吐き気、虚脱感、倦怠感、軽い意識障害(熱疲労)すぐに病院へ搬送
3度:重度 高体温、意識障害、痙攣 (熱射病)すぐに救急搬送
めまい・ふらつきは熱中症の初期症状のため、見逃さないようにしないといけません。
労作性熱中症の場合は、発生環境からすぐに熱中症によるめまいと疑うことができますが、非労作性の熱中症で、自宅発症の高齢者の場合は、熱中症のふらつきを鑑別するのが難しくなります。少し暑くなってのふらつきは常に熱中症を想定した対応・鑑別が必要です。
脳は熱に弱く、熱中症では、脳を冷却して脳のダメージを防ぎ、体温調整機能を低下させないようにすることは重要です。加齢変化による、汗のかける部位の変化でも、若いころは足も含め汗をかけますが、加齢により体内の水分量がなくなるにつれて、下肢から上方に、徐々に汗がかけなくなります。顔や頭部の汗は、年をとっても低下しません。脳の冷却のための合理的な変化がおきています。
汗以外に、脳を冷却するには、頸動脈からの血流で脳を冷やすため、頸部、鼠径部、脇の下に氷嚢などで冷却を試みます。その他には頭部を外から冷やすこと以外ありません。今まで、鼻呼吸の脳の冷却装置としての役割は、あまり報告されていません。体温調節中枢は間脳の視床下部にあります。視床下部は、頭部の外からより、鼻の副鼻腔の一つの蝶形骨洞が外部と最も近い場所です。最近では、脳外科にて、間脳下垂体の手術は、内視鏡を使い鼻の蝶形骨洞を経由して手術が行われます。鼻と脳は数ミリの骨など隔てられているだけですので、鼻からは最も合理的なアプローチとなります。
鼻呼吸による鼻粘膜からの体温調節中枢の深部脳への直接的な冷却や鼻粘膜からの眼角静脈を通しての脳の選択的冷却システムが報告されています。鼻粘膜の鼻汁を利用した気化熱による冷却も考えられます。鼻呼吸による、体温調節中枢がある深部脳の冷却がもっと注目されてよいように思われます。
熱中症予防対策として、鼻の病気があれば治療して鼻呼吸を保ち、少し冷たい加湿した空気を鼻から奥に送ってあげることも対応の一つと考えられます。
➡ 熱中症おこしやすい方と疾患や要因
高齢者:皮膚温度感覚や体温調節機能の低下、基礎疾患による発汗障害や放熱障害
お子さん:発汗機能に未熟性や体の割に体表面積が大きく外部の影響を受けやすい
肥満:脂肪は熱放射を妨げます
体調不良:体温調節機能の低下
脱水状態:
糖尿病:自律神経障害による発汗・体温調節障害、多尿、薬による脱水
二日酔い:アルコールによる利尿作用
心疾患:心機能低下による体内循環量の低下や利尿薬の影響
高血圧症:日頃から塩分摂取制限、利尿薬の影響
精神疾患:無関心・自発性低下による暑熱環境回避をしない、薬の影響 体重増加
*風邪薬
*古いタイプの抗ヒスタミン薬
*咳止め
*トラベルミン(酔い止め)
*精神薬
*抗うつ薬
*パーキンソン病薬
脳内ドーパミン不足を補うため拮抗作用のあるアセチルコリンを抑制するため抗コリン作用の薬を使用
*頻尿薬
*腹痛薬など
上記のことに気を付けながら、温暖化による夏の暑さを乗り切りましょう!
参考資料:ヒトの選択的脳冷却機構とその医学;永坂 鉄夫 日生気誌 37:3-13,2000